


【「今日の格言」と「漢字の読み方」】
湯飲み格言「眼あり眼なしは唐の攻め合い」
読み方「強か」(したたか):「つよか」ではありません。しぶといさま。
九州の方は「つよかー」で正解とします。
購買層が限られておりますので、出版してしばらくすると絶版になってしまいます。
ゆえに、ここでご紹介した棋書もすでに書店の店頭にはないかもしれません。
その点はご了承をお願いいたします。
著者:井山裕太 発行人:小林千寿 発行所:財団法人日本棋院
|
|
 井山裕太20歳の自戦記: 史上最年少名人までの17局 |
感謝を込めて(要約)
第34期名人戦挑戦手合が終了し、共同記者会見がすんで、ほっとしているとき、日本棋院出版部のSさんと観戦記者の秋山賢司さんに呼び止められました。
名人になるまでの打碁集を出さないかというのです。名人になって一、二時間後の急な話です。
私のような者が諸先輩を差し置いて打碁集を出させてもらっていいのだろうかと悩みました。しかし碁に生きる私たちにとって、碁を愛するすべての方に、どんな碁を打ったのかを知っていただくのが最大の仕事です。
そう思うと、ありがたいのはもちろんのこと、意欲も湧いてきました。ここに収めた全十七局は、全力を出し切って満足感にひたった一局、僥倖に恵まれて勝ちを拾った一局、反省がいっぱいの一局とさまざまですが、弱さも含めて、現在の井山裕太が凝縮されています。
私は二十一歳。棋士になって十年目を迎えたところです。これから多くの困難にぶつかるのは覚悟しています。碁も変わっていくだろうと思います。十年目のひと区切りとして、また第二の出発点として、本書は記念作といえるでしょう。
私は自分の力だけでここまでこれたのではありません。
石井邦生先生はご自身の時間を犠牲にして私を鍛えてくださり、折々に重要なアドバイスをいただきました。いくら感謝しても感謝しきれるものではありません。私の対戦相手にも感謝あるのみです。そして一緒に勉強した研究会の仲間もありがたい存在です。どれほど彼らから力をもらったことか。
さらに「頑張れ」と声をかけてくださった地元の人たち。あたたかく見守ってくれた全国の人たち。
すべての人に感謝の気持ちを込めて本書を捧げたいと思います。
2010年8月
井山裕太本書の構成
弾む気持ちで駆け昇った名人への道(秋山賢司)
以上が本書の構成です。
本書は、全17局の自戦記はもちろんのこと、秋山賢司さん(囲碁ライター)の序文、そして、歴代名人のコラムが読み物として、非常にすぐれています。
本書の発行が2010年8月、井山さんが名人位を獲得したのは、2009年、20才4か月のときでした。それは七大タイトル獲得の最年少記録を更新するものでした。
当時の囲碁界はお祭り騒ぎだったように思います。
あれから、15年。井山さんは想像以上の大活躍を見せてくれました。
そして、いまだにトップを走り続けています。
日本の囲碁史上最強である井山さん初の打碁集ですから、価値あるものに違いないです。
観戦記者の見た井山裕太
弾む気持ちで駆け昇った名人への道(著:秋山賢司さん)
観戦記者の見た井山裕太より(要約)
碁を覚えたのは5歳のとき。近くに住んでいたおじいさんの鐡文さんは六段の実力者で、井山さんは星目から教わりました。
鐡文さんは、囲碁に興味を持ってもらうために、囲碁にまつわるいろいろなエピソードを聞かせたそうです。
三国志の関羽の矢疵の話や、遣唐使の吉備真備、本因坊算砂、道策、丈和、秀策、幻庵因碩、木谷実、呉清源、藤沢秀行、趙治勲等々、時代のヒーローの活躍を話し聞かしたとのことです。
鐡文さんが井山少年に強制したのは、右脳の刺激ために左手で打つことだけでした。
井山さんは、5歳で碁を覚えて1年で三段になったそうです。
小学校3年で院生に。6年生のとき71勝8敗(途中46連勝)で入段。
秀行先生の湯河原合宿にも4回参加されて、2回の全勝優勝をされたとあり、それが大きな自信となったとのことです。
名人獲得後のインタビューより、「これからが大変」と言われた時の井山さんの返答は次のとおりです。
「覚悟しています。あんなのが名人かと言われないようにしなくては。中国や韓国の人にも。それに僕たちの世代の励みになればと思います。井山にできたのだから、自分にもできないはずがないと」
歴代名人の見る井山裕太
コラム:歴代名人の見る井山裕太より(要約)
歴代のレジェンドたちからの当時の大きな期待がうかがい知れます。
坂田栄男先生
本書が発行されたのは、2010年8月。
そして、坂田栄男先生が逝去されたのが、2010年10月(90歳)でありました。
「これからが大変ですね。みんなが打倒井山を目指しますから。私からの注文なんてありません。ひとつだけいえるのは、国際棋戦も含めた対局スケジュールに負けない体力をつけることです。私自身が中一日でのタイトル戦でバテた経験があります。そのようなことがないよう、周囲は気を使ってほしいものです。井山くんは日本の宝なのですから」
林海峰先生
「石井邦生さんから大変な弟子がいると聞かされたのは、井山さんが13歳のころだったと思います。もう、かなわないという。弟子自慢と感じたのですが、そうではなかったですね。16歳で早碁棋戦で優勝したり、最年少記録で棋聖戦、名人戦のリーグに入ったりでなるほどと認識を新たにしました。負けにくく、取りこぼしが少ない。形勢が悪くてもジタバタせず、じっとチャンスを待つ。弱点を探そうにも見つかりませんね。国内の棋戦はますます活躍するでしょう。問題は国際棋戦です。まだ、結果は出ないとしても、井山さんなら十分やっていけると思います。世界一になる日を楽しみに待つことにしましょう」
石田芳夫先生
「阿含・桐山杯を優勝したのが16歳でしたか。あとは爆発したかのよう。17歳でリーグ入りした棋聖戦は残留し、18歳での名人リーグ入りではいきなり挑戦者になった。昨年は持ち前のバランス感覚に加え、迫力が出てきた。その迫力で張栩名人を終始押しまくったような印象でした。第3局なんか、コウに強い張栩名人が歯車を狂わされている」

「私が立会人をつとめた昨年の第1局も印象に残っています。黒△のカドに対して井山くんは白1、3とツケ切った。しかし、黒4、6から14と二子を制され、一見して白が苦しそうではないか。控室で検討したのですが、なかなかうまくいかない。井山くんは最もシンプルな方法を選んだ。すなわち白17のトビから19とツケたのがうまい。白25まで。あっという間に整形して、我々は驚くやら感心するやら。本局はシリーズ唯一の負けでしたが、負けても強しと思わせました。これからは国際棋戦ですね。期待しています」
大竹英雄先生
「20歳でチャンピオンというのは大変な偉業です。前年、最初の名人戦挑戦者になってからの1年間の努力は、いくら評価しても評価しすぎることはないでしょう。名人になった井山さんは、リーダーの資格を得たという気持ちで精進してもらいたい。世界中の棋士が井山さんを目標とするようになれば、どんなにすばらしいことでしょう。いつ見ても感心するのは、井山さんの碁に模倣がまったくないことです。自分の頭で考え、実行している。私は井山ファンの一人なのです」
趙治勲先生
「井山さんは期待の星です。日本のすべてのタイトルを取るくらいの活躍はできる人です。世界の第一列に並べる人だと思います。世界に向かって突き進んでほしいですね。昔は名人ですといってデンと構えていればよかったのですが、いまはそうもいきません。名人の価値が低下したのです。日本の名人が世界の名人であると胸を張っていえるようになりたいものです。そこへ現れたのが井山さんです。井山さんならやってくれると信じるから期待するのです。目標を一本に絞って頑張るべし」
小林光一先生
「いずれ出てくるは思いましたが、こんなに早く昇りつめるなんて予想外でした。二十歳の名人はこれからなかなか破れない記録でしょう。張栩くんとの二回のシリーズは熱心に見ました。一回目はともかく、二回目は勝ちみの多い手を選ぶのはもちろん、一手一手にすごみのようなものがうかがえました。最近は碁がずいぶん変わりました。すぐケンカになり、油断も隙もあったものではない。現代は少々のかしこさより、力がないとやっていけません。そう考えると、井山くんの出番はますます増えるでしょう。打撃の力だけではなく、相手の打撃を吸収して撥ね返す力も超一流です。張栩、山下敬吾、羽根直樹、高尾紳路、河野臨、面白い時代になったというべきでしょう」
武宮正樹先生
「石井邦生さんから何度も聞かされました。入段してからはとくに注目していました。打ちっぷりがとてもいい。強くなりそうだと思ったものです。すなおでいきいきして、打つ手が堂々としている。理屈ではなく、自分の感性を信じて打っているのが分かります。まっ先に並べたくなる碁です。さわやかな気持ちにさせてくれます。」

「最初に名人に挑戦したときの第1局です。黒1と張栩名人が迫ったとき、井山くんは白2と肩に行った。これがじつに自然なのです。黒△と低いので、すなおに上から利かす。難しく考える必要はありません。黒3から7となったとき、白8と戻ったのが自然で厚い。勢い黒9、11と出切りますが、この戦いに不利は考えられません。黒15とハサまれ、右上の白一子の進退は不自由でも、碁盤を大きく見れば、黒1の一子が白の厚みに近寄りすぎているのが分かります。独自の棋風を追及して、いま以上に感動を与えられる棋士になってほしいですね」

井山裕太20歳 はたち の自戦記 史上最年少名人 の17局
第16局:コウの大激戦を制す
本書より
第16局 コウの大激戦を制す
以下、本書より(要約)
「迎えた名人再挑戦。第1局は半目負け。計算違いをしての半目負けでした。張栩さんたちとの深夜におよぶ検討でも分からず、後日勝ち筋が見つかりました。だから負けたのは仕方ないと割り切ることができたのです。第2局は自慢できる碁ではないけれど、いっぱいに打てたという充実感みたいなものがありました。」
「第3局の対局場は宝塚。私にとってホームゲームのようなもので、前夜祭も顔見知りが多く、声援を受けて戦うことができたと思っています。このシリーズ最も印象に残る一局です。あちこちにコウができてクラクラしそう。打ちすぎや見落としはあったけれど、それでも張栩さん相手に力負けしなかった点で、小さくない自信になりました」
負けにした
第34期 名人戦七番勝負 第3局
2009年9月24日、25日
兵庫県宝塚市「宝塚ホテル」にて
黒:張栩(名人)、白:井山裕太(八段)
実戦図:黒59まで

棋譜再生
実戦図:黒59まで
以下、本書より(要約)
「黒37が好点。白40と急所に迫って、控室は白良し説だったそうですが、私は難しいと思ってました」
「黒41はいっぱいの頑張り。進みすぎの感があり、これをとがめる手も考えましたが、思い直して、白42でがまんしました。まだ全体の黒への攻めをみています。」
「ここから白の流れが悪くなる。まず、白44。それ以上に責任が重いのが46でした。白46を打った瞬間、ひょっとしたら黒47があるかもしれない、こられたら困るなと思いました。気がつくのが遅すぎます」
「案の定、黒47が厳しかった。急所を制され、ダウン寸前です。白52とダメをつながったのも辛い限り。黒53、55で右辺に理想的な地を作られました。この碁をダメにしたと思った瞬間です」
「黒57、59と追及はますます厳しい。ここから白が追い上げるのは不可能に近いと思います。しかし、簡単にはあきらめるわけにはいかない。辛抱を重ねて黒についていくしかないと決めました」
第2、第3のコウ
実戦図:黒163まで
実戦図:黒163まで
本書より(要約)
「白2とコウを取ってコウにはなかなか負けず、明らかに黒は変調です。延々とコウが続きます。中央のコウを争ってる最中に右辺と右上で第2、第3のコウが生じ、目がまわりそうです。」
「白46、48、50で行けると見通しがつきました。もう黒にコウダテがなく、51とコウをツグくらいのもの。白52から54とツイでこわいことはなくなりました。残る問題は右辺と右上のコウだけ。しかし、これがややこしいのです」
充実の一局
投了図、白1(実戦の白246)からの参考図:黒2~白9まで

投了図、白1(実戦の白246)からの参考図:黒2~白9まで
本書より(要約)
「最後は白1(実戦の白246)の一手だけ見ていただきます。これで張栩さんは投了です。続けて打つとすれば、黒2ですが、白3、5から7と切っていい。黒8に白9と差し込んで白の取り番のコウ。黒のコウダテは盤上のどこにもありません」
「ご覧のように悪手や打ちすぎは多いけど、苦しい前半を何とか耐え、張栩さんのコウの脅しにも屈しなかった。力を出し切り、充実した気持ちで一局を打ち終えることができた爽快感でいっぱいでした」
246手完、白中押し勝ち
(。・(エ)・。)ノ↓ランキング参加中、ポチ応援をいただけると励みになります。



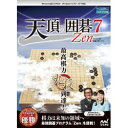 マイナビ 天頂の囲碁7 Zen(対応OS:その他) 目安在庫=△ |
 基本布石事典(下巻)新版 星、小目、その他 [ 依田紀基 ] |
 ヒカルの囲碁入門 ヒカルと初段になろう! [ 石倉昇 ] |
 ひと目の詰碁 (マイナビ囲碁文庫) [ 趙治勲 ] |







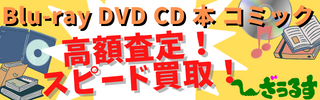

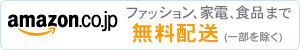




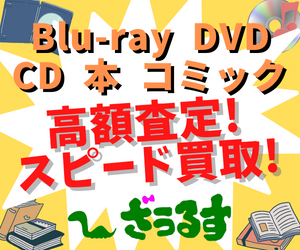


.png)



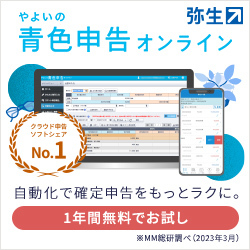
おはようございます。
返信削除「棋書の紹介その58(井山裕太20裁の自戦記)」拝読いたしました。
「強か」(したたか)ですね。
九州は「つよかー」が九州らしくていいですね。
Ounaさま。おはようございます。
削除コメントをありがとうございます。